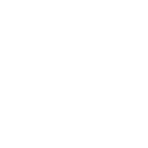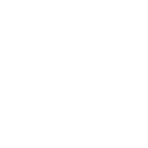去る令和7年1月24日、25日に、愛知県立名古屋盲学校を主管校として、「第65回弱視教育研究全国大会(名古屋大会)」が愛知県立名古屋盲学校、ウインクあいちで開催され、主に、盲学校教員、弱視教育に携わる方、眼科医、視能訓練士等様々な職種の方々が全国から参加されました。
大会2日目に行われたシンポジウムにおいて、名古屋盲学校の小学生児童への支援事例をモデルケースとし、このケースに各分野から関わった専門家が発表を行うとともに、愛知県における医療、教育、福祉の連携に関する今後の展望と課題についての討論が行われましたので、報告いたします。
シンポジウム概要
・日時:令和7年1月25日(土)10時20分~11時50分
・会場:ウインクあいち 10階1002会議室
・テーマ:地域の視覚障害児の学びを支える地域支援・機関連携の在り方について
-愛知県における現状と教育・医療・福祉の連携事例からの検討-
・登壇者
司会:相羽大輔氏(愛知教育大学)
シンポジスト
教育分野:前田政治氏(愛知県立名古屋盲学校)
福祉分野:池内達彦(社会福祉法人名古屋ライトハウス情報文化センター)
医療分野:川部幹子氏(医療法人TM会コスモス眼科)
当事者家族:当事者児童のお父様
指定討論者:池谷尚剛氏(岐阜大学名誉教授)
事例発表
当事者ご家族のお父様からは、当事者児童の生い立ちを始め、発達障害との診断はあったが、同時にロービジョンでもあったため、長期に渡り支援に苦戦していたが、愛知教育大学の相羽氏への相談を皮切りに視覚障がいの身体障害者手帳を取得し、道が開けたとのお話をされました。また、ご家族の葛藤や苦しみ、視覚障がいの身体障害者手帳取得に対する前向きな思い、当事者本人が交流学級で話された内容などが発表されました。
前田氏からは、名古屋盲学校における地域支援の課題について発表があり、支援が行き届いていない現況、支援担当者の育成に工夫が必要であるとの指摘がなされました。
池内からは、手帳取得前に実施した歩行訓練について報告をさせていただきました。主に転居先から通学している学校までの単独歩行の訓練や歩行経路内における見え方の確認について報告を行いました。
川部氏からは、当時者児童の手帳取得までの医療的な経緯や、身体障害者手帳取得により「視覚障がい者である」ことを行政に認知される必要性、また、取得により福祉サービスが可能になる等、手帳の申請・取得する意義について医師としての立場から発表されました。
討論内容
司会の相羽氏からは、愛知県下における視覚障害児の学びについての地域の小・中学校へ調査を行った結果、盲学校との連携が不足している事、調査内では明確な眼疾以外に、斜視、色覚多様性、中枢性視覚障害等、視覚による認識に何らかの困難を有する者が含まれており、広い対象への支援拡大の必要性が指摘されました。また、指定討論者の池谷氏からは、岐阜盲学校の連携課題について、従前は視覚障害児者への地域ネットワークの形成・維持であったが、現在は視覚支援ニーズを有する児童生徒(発達障害児)の見えにくさへの支援に変化している等のお話がありました。
以上からシンポジスト、会場内での討論の結果、今回の事例をモデルケースに留めず、何らかの形で枠組み化する必要性があるとまとめられました。
まとめ
今回のケースは教育、医療、福祉、そしてご家族とも連携が取れた好例といえるでしょう。名古屋ライトハウスの歩行訓練としても、今回上記のケースに関わり、微力ながら支援ができたかと考えています。
最後に、歩行訓練士はそのニーズの増加に対し人数が不足していることが喫緊の問題となっており、直近ではネットニュースでも大きく取り上げられました。
今後ニーズの増加が予想される医療・教育・福祉の連携においても、歩行訓練士の存在は欠かせないものと考えています。また、視覚障害者の自立において、一人で安全に歩き、目的地で用務を済ますことができるようになる歩行訓練は、当事者の生活の質に大きな影響を及ぼします。
この寄稿をお読みになられた方に歩行訓練士の存在を、そして視覚リハビリテーションの重要性を少しでも知って頂ければ幸いです。